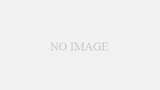ナチュラルボーン多問題!
3歳から貧困・カルト2世・ヤングケアラー、多問題サバイバーの天馬です。
灼熱列島、朝晩は少しづつ涼しくなり「虫の息」ちゃう「虫の音」が心地よい。
ついつい、「ポイ活」で貯めたポイントを足して新米を購入。 やっぱりお米はおいしいね、と噛みしめる日々。 農家の方、運んでくれる方、売ってくれる方、ありがとう~!
今日もご飯が食べられるという幸せ。 日本中のこども達が味わっていますように。
◆国がこども食堂に応援するってさ!
さて、こども食堂の生みの親と言われる近藤さんが一線を引くと言いだした訳。 インタビュー記事を読んで、激しく同意した天馬。 どういうことなんかい?と、さらにサーチを続けてヒットしたのは、こんな記事。
2020年の厚生労働省の広報誌(こんなん出てたのね。不勉強ですんまそん)
「こども食堂応援企画」ということで、NPO法人全国こども食堂支援センターむすびえ理事長の湯浅氏との会談を掲載している。
湯浅さんは、「年越し派遣村」(※)の村長さんを務めた方と言った方が皆さんご存じかも。 「反貧困」の活動家としてご活躍されている。 (※「年越し派遣村」2008年のリーマンショック時に解雇され行き場を失った労働者の人を支援するために東京・日比谷公園に設置された臨時避難所)
で、ほうほうと読んでみたんだけど・・・。
ごめんなさい。 正直いって、違和感しか感じなかった。 ええ話のはずなのに。
元当事者ゆえに斜めにモノを見る癖がある天馬。 だから素直に受け取れないのかもと思い何回も読み返す。
滑る目を叱咤しながら読んで、何とか湯浅氏が目指していることは「理解できる」とは思った。
でもでも、ちょっと違うんじゃね?と。
AIに激しく劣るけど、以下、天馬なりの解釈。
OECD(経済協力開発機構)が「所得の中央値の半分以下」を「相対的貧困」と定義しており、日本だと「7人に1人が貧困状態」だそうな。(この記事は2020年。最近の記事だと9人に一人とも。少し持ち直したのか?いや、確実に貧困率上がってる気がするけど…)
でも、この「貧困状態」にもレベルがあるらしい。
「今日食べるものがない!」という極貧家庭やその子供たち(記事では「深刻な虐待や非行、不登校などの専門的な支援を必要とする」子供も含む)を「赤信号」。
飢えるほどではないがちょっと何かあったら極貧に陥る可能性が高い家庭やその子供を「黄信号」に分けている。
でね、赤信号の子供たちは可及的速やかに「児童相談所」や「行政の担当部署」が動くべきだと。
ふむふむ、そうよね。 でもさ、児相の人手不足・スキル不足、縦割り行政による連携不足は相変わらずじゃね? と、突っ込みたい気持ちは置いといて。
で、「黄信号」の子供たち。
相対的貧困家庭だけど、今日食べるものはあって、普通に通学している。 記事にあった「修学旅行の旅費が出せず欠席し、そのことでいじめられて・・・」という例えは分かりやすい。
そう、天馬もパンの耳とはいえ食べるものがあり、お下がりだけど洋服や学用品は持っていた。 だけど、年度初めに「就学援助費申請書」をもらう「貧困家庭」であった。
この定義なら、天馬も「黄信号」の子供だわな。
この件でからかわれたことはないが、子供心に辛い思い出として残っている。 性格ゆがんだ(笑)のも、子ども時代の多問題当事者としての辛さが一因だと思ってる。
だからこそ、今の「黄信号」の子供達が「青信号」の顔をしてこども食堂に通えるようにあってほしいというのは、非常にありがたいとも思う。
だけどさ、問題はこのあと。
なんとね、こども食堂を担う民間団体に「黄信号」の子供たちが「赤信号」に転落しないような支援をしろってさ。
「1団体に800万円超の予算」をつけるから、黄信号の子供たちへの訪問をよろしくねって。
ちょっと待てい!
心臓バクバク、血圧上昇。
これって、「国がこども食堂に支援をしていくから、支援対象児童の見守り支援をやってね」ってこと?
誰か、天馬の読み間違いだと!違う!って言ってくりゃれ・・・
◆こども食堂にお金だすってよ!
全国1万か所まで増えたという「こども食堂」。
今や、こども食堂に来るのは子供だけではない。 子育て中のママさん、近所のジジババ、もろモロ師岡。 そう、子供に限らず「地域の居場所」という役割を担っている! だから、国としては予算つけてバックアップします。
人とカネに困っている団体としちゃ、とってもありがたし!
ただし、「黄色信号の子供達の見守り支援」と引き換えですと。
えーっと、政治家と役人の大好きな「ホメ殺し」ですか? 札束で頬っぺたをひっぱたかれるような気持になったのは私だけ?
天馬が地域包括支援センターという高齢者福祉の窓口で働いていた数年前のこと。
8050(高齢者とその子供世代だけで孤立した世帯)+お孫ちゃん達の世帯があった。
介護が必要な高齢者世代。 失業や疾病で働けない子世代。 持ち家や高齢者世代の年金があって、そのままだと生活保護は出せない微妙な状況。
一番上の子がヤングケアラーになって、下の子供達の世話と高齢者夫婦の世話もしてて。
当然、介入が始まったけど、やはり行政だから部門が分かれていて。 天馬たち高齢者班は、ジジババのケアをどうするかを中心に動く権限しかない。 お嫁さんの精神疾患や生活費は生活支援や若い世代の担当がいて。 子供達の養育をどうするかは、子どもの担当部署がいて。
だけど、家族をまるっと統括する行政部門がない。
ゆえに、各部署に保健師やソーシャルワーカーはいるけど、それぞれの管轄でしか動けない。
高齢者へ介護のサービスを入れたくても、利用料が発生すると一家の生活費が回らない。 子世代は失業と病気で働けない。 子供達は何とか学校や保育園に通っているけど、家で勉強する、部活に参加する、ましてや余暇活動を楽しむなんて夢のまた夢。
世帯分離するにしても、いろいろな障壁で身動きが取れない。 刻々と、ジジババの要介護化は進むし、子ども達も日々成長していくのに。 全体会議で、ついつい子供世代・孫世代のこと突っ込んじゃう天馬。 だけど、高齢者班は高齢者のことだけやって口出しスンナという感じで。
結局、天馬たちにできたのは高齢者世帯にケアマネジャーを付けることだけ。 地域包括支援センターはさらに後ろの後ろでの支援になり・・・
役所の支援が縦割りなのは重々承知。 それが、今の行政の限界かと。
多問題家族の課題解決のためのアプローチを統括するのは誰なんだよ! と、何度か息まいてみたけど、「しょうがないよ」とあきらめ顔の上司や保健師達。
そう、行政と福祉の専門職が集まってても速やかな解決にはほど遠い状況なのさ、現場は。
明らかに「赤信号」の子がいたって、その先の支援に中々つながらないのにさ。
10年以上前に、近藤さんがこども食堂を始めるきっかけになった「バナナ1本」の子だって、支援が間に合わず養護施設に行ったというじゃない。
厚労省の記事では、いわゆる専門家達がこども食堂のスタッフに支援が出来るわけないと批判的だと批判しているように感じるけど。
批判的なんじゃなくて、問題が複雑かつ微妙で専門家でも難しいんだよ。 さらに、縦割り行政が邪魔してる。 ようやっと専門家が道筋をつけて支援を始めようとしても、色んな制約で円滑に進まない。 そんな中でボランティアの人が頑張って活動して下さっても、双方に何かあったら取返しつかないじゃん?という縦割り行政への批判なんじゃないかと。
百歩譲って、湯浅さんたちが言うように黄信号の子ども達を発見した場合。
訪問して状況把握なんて、なんの法的根拠があって介入できるのさ?
正直、問題を抱えている家庭が「あら、いらっしゃい♡」と歓待してくれるかな? しかも、こども食堂はその家庭の地元だろ?
「うちは地域で貧乏と思われている」 「こども食堂の人が探りにきた」 「虐待でもしていると思われたんだろうか」
そんな思いをさせたら、あっというまに「扉」はしまる。
「あんた、あそこ(こども食堂)で何かしゃべったの?」 「もう、(こども食堂に)行くんじゃないよ!」
そして、こどもは居場所をなくす。
あーもー、目に浮かぶようだわ。
こども食堂って、そこに行けばお腹と気持ちがちょっと温かくなる。 安心して過ごすことができる。 そんな場所でいいんじゃないかな? それだって運営は大変だろうし、続けてくれたら「御の字」だよ。 だって、ボランティアだもん。
これが、天馬の最初に抱いた感想です。
→貧困ということ・・・⑥に続く