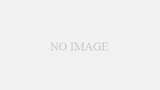ナチュラルボーン多問題!
3歳から貧困・カルト2世・ヤングケアラー、多問題サバイバーの天馬です。
長い前置きで息切れしました。
天馬は短距離走者なのよ!と言い訳しつつ、また走り出します。
◆「こども食堂」辞めるってよ?
こども食堂のことを調べ始めた時、グーグルさんが最初に知らせてくれたのが、この記事。
「こども食堂から一線を引く」 《こども食堂》の名付け親が決意した背景 ボランティアでできる支援には限界がある(東洋経済オンライン2025/5/30より)
https://toyokeizai.net/articles/-/880254?page=2
これはこれは! どないしはったん?
近藤博子さんは、こども食堂の生みの親と言われていて2012年から東京都大田区でこども食堂を始めたパイオニア。
元々歯科衛生士をされていた近藤さん家庭の事情で働き方を調整することに。 ※ここでも、家庭の事情で働き方をチェンジしなくちゃいけないのは、やっぱり女性なの?と思ったけど、また脱線しちゃうから我慢我慢(笑)
以前から興味のあった「歯と健康と食」をテーマに、「だんだん八百屋」を開設。 地域住民との交流をしていくうちに、地元の学校の先生から「給食以外は、1日バナナ1本で過ごしているこども」の話を聞かされた。 その中で色々と考えて「こどもが一人で来ても怪しまれずに入れる食堂」をコンセプトに、2012年からこども食堂を始められたそうな。
その後もずっと活動を続けられ、吉川英二文化賞等数々の表彰・受賞をされ、石破総理も見学に来たことがあるそうな。
そんな第一人者が、こども食堂の一線から身を引くと公言したとは、これいかに?
以下、本文から。
――「こども食堂」から一線を引く決意をされたのは、なぜなのでしょうか。 「こども食堂は子どもの貧困解消に役立つ、良いことだ」というイメージが広がりすぎています。企業も、こども食堂に寄付をすることで、子どもの貧困対策に貢献しているというイメージが生まれています。 でも、月に1度や2度、あるいは週に1度、食事を提供しても、おコメを2キロ、3キロ渡しても、子どもの貧困は何も変わりません。これまでこども食堂を続けるなかで、子どもの状況はますます苦しくなっている現状を目の当たりにしました。 子どもの貧困は、国や自治体が、親の就労問題や、子どもの教育問題、住宅問題などに真剣に取り組まなければ解決しません。
うんうん、のっけから激しくうなずいてしまうわ。
さらに読み進めていくと・・・
◆こども食堂が急増したのはなぜ?
近藤さんは、こども食堂が急増した理由について3つ述べている。
①食事を作って一緒に食べる、お弁当にして配るのは始めやすい。 ②みんな、お腹を空かせている子供がこんなにいると思わなかった。 ③子どものために何かしたいという人がたくさんいる。
確かに、「こども食堂」には、モノグサ天馬ですら「やってみようかな」と思わせる魅力がある。
実際に活動を始めている先達にリスペクトしかない。
だってね、開設するの大変よ、ホントに。
実際に始めてみるとどんなことが必要になってくるのか。
まず、お金。
そうよね、食材と場所の確保は最大のミッションだわな。
社会福祉協議会の人も、やりたいと手を挙げてくれる人はたくさんいてありがたいと。 だけど、実際に運営を始めると色んな課題が出てくる。 食材の確保、水光熱費や会場の手配(公の場所を貸してくれることもあるが、厨房設備を備えているところがあまりない)等々。 自分たちでやってもらうことになる。
助成金も出るようになったとはいえ、獲得するのは大変。 全くの素人さんが、申請書を不備のないように書き上げるのは至難の業。 そして、獲得したらしたで活動して報告書を提出しなくちゃいけない。 年に1回やればいい地域のお祭りなどとは違って、開設したら「続ける」ことがマスト。
で、次に人。誰でもいいって訳にはいかない。
7・8年前だったかな。 地域包括支援センターにいた頃。 地域の会議で、1人でこども食堂を始めたおじさんとご一緒した。 1人でもやる気満々で始めたけど、やっぱりスタッフが必要となり。 ボランティアを募っても誰も来られない時もあり孤軍奮闘していると。
しばらくして、子供達に勉強教えてくれる学生を求めて大学の多い地域に引越しちゃいました。
自分の生活もあるし、必ず決めた日に開催しなければならないというプレッシャーは強い。 食物だから衛生面にも気を遣うし、寄せられた食材や寄付をどう有効に使うかも大変。 スタッフがそろわなくても、開催日には笑顔で「本日開店」しないとあかん。
地域性も大事。 古くからの住民、自治会、商店会、民生委員とも仲良くせなならん。 これが、言いたかないけど「老害化」しているところも多い。 当事者である高齢者問題だとしても、口は出すけど手を出してくれる人は希少。 しかも、成功体験?のある老人ほど、若い人の意見を聞かないよね・・・。 「会長」とか「商店会長」とかに拘り、決定権は自分にあると勘違いするジジ様とか。
食中毒でも起こしたらどうする 場所を貸して悪い子達のたまり場になったらどうする と、ネガティブな意見を言い募る。
近藤さんがインタビューでおっしゃっていること、デジャブかと思ったほど。
こども食堂に必要なのは「お金」と「人」。
だけど、その基盤はまだまだ脆弱。
「温かい人達」の善意が広がり、今では1万か所まで増えたこども食堂。 企業も食材を寄付したり、場所を提供するから運営よろしくねなんて施設も出てきたり。 倍率高いとはいえ助成金も出るようになり、ACジャパンのCMでも大々的に取り上げられるほどになった。
だけど、認知度が上がったことにより「なんか食べさせてくれるんでしょ」と押しかけてくる人もいるらしい。 当然、キャパオーバーだろうし、当初のコンセプトと違ってくるよね。
ましてや「国の補助を受けてるなら、税金払っている地域住民も食べさせろ!」みたいな人が来るならば、勘弁してよと思ってしまう。
そう、あくまでも地域のボランティアじゃないの?
今回調べた結果、思いのほか「やりたい!」という人が多いことはよかった。 確かに、地元の「こども食堂MAP」を見ると、例のおじさんが引っ越していった時より確実に活動団体は増えていた。
でもね、月1回とか2回とかの開催団体ばかり。
本当に飢えている子供たちに足りるんだろうか、と。
と、リサーチを続けたら、こんな記事も。
ちょっと古い記事になるけど、2020年の厚生労働省の広報誌。
子ども食堂応援企画~子ども食堂、その先にある誰も取りこぼさない社会づくりへの挑戦 (広報誌『厚生労働』2020年10月号 発行・発売:(株)日本医療企画)
えー!こんなことになってたんだ!
そりゃ、近藤さんが一線引くと言いだすわけだわ、と納得しました。
貧困ということ・・・⑤に続く。